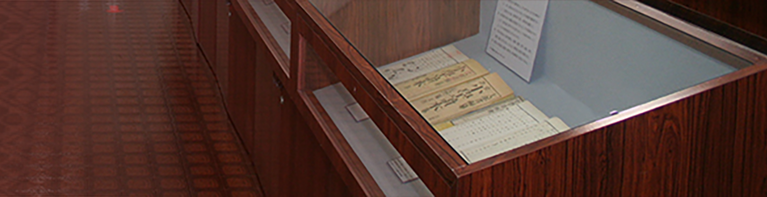|
年号(西暦)
|
沿革
|
|
昭和 9(1934)年
|
東京書籍株式会社創立25周年記念事業として,我が国初の教科書図書館の建設を企画
|
|
昭和11(1936)年
|
東書文庫と命名する 6月25日開館 鉄筋コンクリート造,延床面積734㎡ 東京書籍翻刻発行の教科書,寄贈図書,収集した図書等約5,500点を公開
|
|
昭和13(1938)年
|
文部省より明治時代を中心とした検定教科書等(小学校・旧制中学校・高等女学校・実業学校・師範学校約47,000点)の寄贈を受ける
|
|
昭和20(1945)年
|
空襲が激しくなり,疎開準備中に終戦
|
|
昭和24(1949)年
|
日本橋三越(東京都中央区)にて,東京書籍が「教科書変遷展」を開催し,東書文庫所蔵資料を出展
|
|
昭和37(1962)年
|
東書文庫内に展示室を新設
|
|
昭和54(1979)年
|
東京書籍創立70周年を記念して増築,10月完成 延床面積1,359㎡となる
|
|
教科用図書目録第1集(旧制中学校・実業学校・師範学校等)を発行
|
|
昭和56(1981)年
|
教科用図書目録第2集(明治初年から戦前までの小学校関係教科書・掛図等)を発行
|
|
昭和57(1982)年
|
教科用図書目録第3集(戦後の小学校・中学校・高等学校の教科書等)を発行
|
|
平成 5(1993)年
|
東京書籍新本社ビル落成記念「東書フェア」で本社にて,東書文庫所蔵資料を出展
|
|
平成10(1998)年
|
紙の博物館(東京都北区)にて,東書文庫所蔵資料による「紙から見た教科書」展を開催
|
|
平成11(1999)年
|
東京都「北区指定有形文化財(建造物)」の指定を受ける
|
|
平成19(2007)年
|
経済産業省による「近代化産業遺産」に認定される
|
|
平成21(2009)年
|
近代教科書関係資料として所蔵資料のうち76,420点が国の「重要文化財」の指定を受ける
|
|
印刷博物館(東京都文京区)にて,東京書籍創立100周年記念「近代教育をささえた教科書 -東書文庫コレクションを中心として-」展を開催し,東書文庫所蔵資料を出展
|
|
平成26(2014)年
|
謙堂文庫より往来物を中心とした資料約3,300点を譲り受ける
|
|
平成27(2015)年
|
国宝重要文化財等保存整備費補助金を受け,「近代教科書関係資料美術工芸品保存修理事業」開始
|
|
平成29(2017)年
|
国文学研究資料館(東京都立川市)のプロジェクト「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」への参画を決定
|
|
平成30(2018)年
|
国文学研究資料館が運営する「新日本古典籍総合データベース」において旧謙堂文庫資料の画像データ公開が始まる
|
年号(西暦)
沿革
|
昭和 9(1934)年
東京書籍株式会社創立25周年記念事業として、我が国初の教科書図書館の建設を企画
|
昭和11(1936)年
東書文庫と命名する 6月25日開館 鉄筋コンクリート造,延床面積734㎡ 東京書籍翻刻発行の教科書,寄贈図書,収集した図書等5,500冊を公開
|
昭和13(1938)年
文部省より明治時代を中心とした検定教科書等(小学校・旧制中学校・高等女学校・実業学校・師範学校47,000冊)の寄贈を受ける
|
昭和20(1945)年
空襲が激しくなり,疎開準備中に終戦
|
昭和24(1949)年
日本橋三越(東京都中央区)にて,東京書籍が「教科書変遷展」を開催し,東書文庫所蔵資料を出展
|
昭和37(1962)年
東書文庫内に展示室を新設
|
昭和54(1979)年
東京書籍創立70周年を記念して増築,10月完成 延床面積1,359㎡となる
教科用図書目録第1集(旧制中学校・実業学校・師範学校等)を発行
|
昭和56(1981)年
教科用図書目録第2集(明治初年から戦前までの小学校関係教科書・掛図等)を発行
|
昭和57(1982)年
教科用図書目録第3集(戦後の小学校・中学校・高等学校の教科書等)を発行
|
平成 5(1993)年
東京書籍新本社ビル落成記念「東書フェア」で本社にて,東書文庫所蔵資料を出展
|
平成10(1998)年
紙の博物館(東京都北区)にて,東書文庫所蔵資料による「紙から見た教科書」展を開催
|
平成11(1999)年
東京都「北区指定有形文化財(建造物)」の指定を受ける
|
平成19(2007)年
経済産業省による「近代化産業遺産」に認定される
|
平成21(2009)年
近代教科書関係資料として所蔵資料のうち76,420点が国の「重要文化財」の指定を受ける
印刷博物館(東京都文京区)にて,東京書籍創立100周年記念「近代教育をささえた教科書 -東書文庫コレクションを中心として-」展を開催し,東書文庫所蔵資料を出展
|
平成26(2014)年
謙堂文庫より往来物を中心とした資料約3,300点を譲り受ける
|
平成27(2015)年
国宝重要文化財等保存整備費補助金を受け,「近代教科書関係資料美術工芸品保存修理事業」開始
|
平成29(2017)年
国文学研究資料館(東京都立川市)のプロジェクト「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」への参画を決定
|
平成30(2018)年
国文学研究資料館が運営する「新日本古典籍総合データベース」において旧謙堂文庫資料の画像データ公開が始まる
|