1.公衆衛生
明治時代から終戦まで、全学年の必修教科であった修身には、儒教思想のみならず日常生活の心得や公民知識の普及も含まれており、国民の思想や生活信条の形成に重要な役割を果たす教科でした。明治初頭には、さまざまな修身教科書が「養生」「清潔」「食物」等の項目を設けて健康増進の必要性を説いています。また公衆衛生の概念は、教科書の国定制度が始まる前の明治30年代の検定教科書に「公衆衛生」「公徳」として登場しています。
それでは1904(明治37)年4月から使用された第一期国定の修身教科書を見てみましょう。

「第13 しんたいについてのこころえ」
尋常小学修身書
第4学年 児童用
1904(明治37)年 文部省
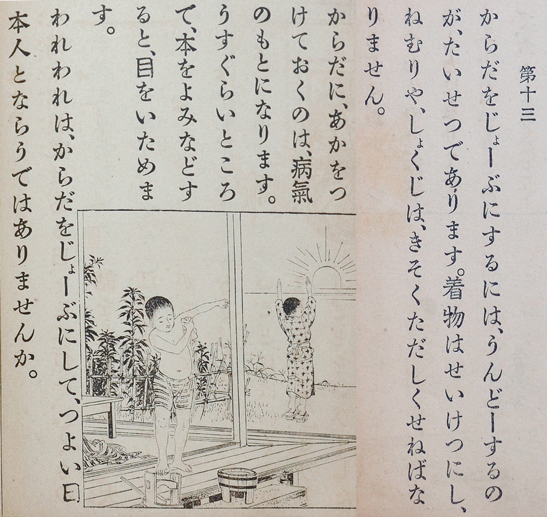
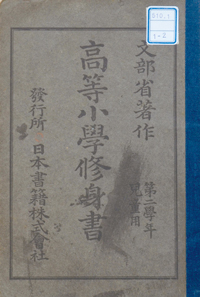
「第21課 公衆衛生」
高等小学修身書
第2学年 児童用
1904(明治37)年 文部省
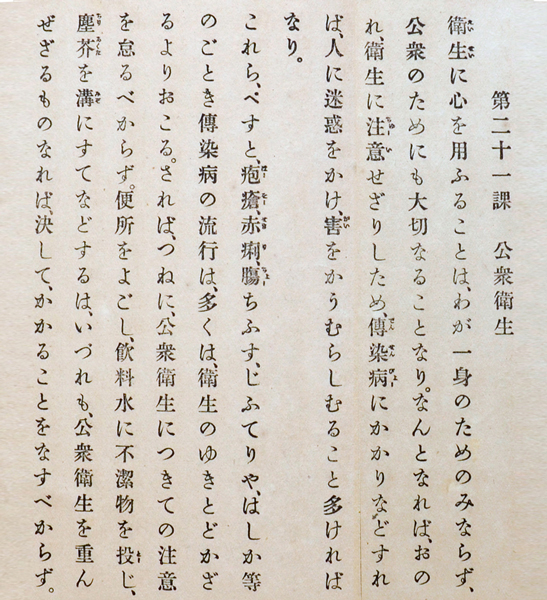

「第九 からだを丈夫にせよ」
尋常小学修身掛図
第2学年用上
1919(大正8)年 文部省
(北澤清貴)

