明治初年の国語教科書と野球
学制公布の翌明治6(1873)年、文部省は洋学者田中義廉編『小学読本』(4巻)と、国語学者榊原芳野編『小学読本』(6巻)の2種類の国語教科書を刊行した。前者は冒頭の課を除いては、当時アメリカで普及していたウィルソン・リーダーの翻訳であり、後者の伝統的な国語教材観による本と比べて、文明開化の世相にマッチし、より多く使われた。
翻訳の原典のリーダー第1巻に、baseballという単語は使われていないが、少年達がボールを投げバットを構えて草野球をしている教材がある。それを『小学読本』初版本では、原典の5行目から取り上げ「彼らは球を蹴て遊べり、汝はそれを見しや、・・・」としているが、唐突すぎてよく分からない。そこで、翌年の改訂版では「群児相集り、毬を投げて、遊び居れり」と改めている。しかし、次の「彼らの棒を持てるは、投げたる毬を、受留めるを以て」の"受留る"は、"打つ"としたほうが分かりやすかったであろう。
わが国では明治10(1878)年に「新橋倶楽部」という初の社会人チームができ、90年ごろまでには、学校の間で試合も行われるようになったが、それ以前にこの読本を学んだ小学生がいたということは興味深い。ちなみに、baseballを「野球」としたのは、第一高等中学校(のちの一高)の生徒、日本の教育者、元野球選手 中馬庚で、明治27(1894)年のことである。
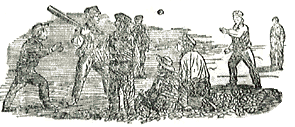
《英文原典》
Do you see the boys at play? Yes;I see them! What do they play with?
They play with a ball;and the ball is as large as my head.
They kick the ball. Do you see them do it? No;but I see them hit it with a club!
Is it a hard ball? No;it is a soft ball;and if it hits them it will not hurt them,
Boys love to play ball. It is good for them to play;but they must not play all of the time.
Do not play too long when it is a hot day. You must not get too warm, for that will hurt you.
(谷勝)

