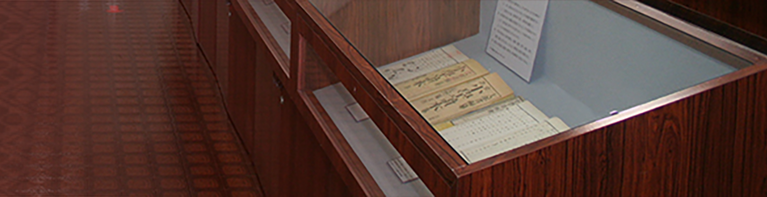東書文庫は、日本で最初にできた教科書図書館で、昭和11(1936)年6月の開館以来、時代と共に教科書を収集・保存してきました。正式名称は「東京書籍株式会社附設教科書図書館 東書文庫」と言います。
その成り立ちは、母体である東京書籍創立25周年の記念事業によるものです。東京書籍は明治42(1909)年の創立ですが、三代目石川正作社長は、「今のうちに日本の教科書を蒐集し保存をしないと何れ散逸してしまう」ことを惜しみ、研究利用の設備も設けた専門図書館の設立を決めました。
昭和8(1933)年に「改正図書館令」が公布され全国各府県に次々と図書館が設立されていきましたが、教科書中心の教育図書館は見当たりませんでした。石川社長は、早速文部省図書局長の芝田徹心氏に相談し、氏の熱心な支持も受け着工しました。
工事は新社屋建設と相前後して急ピッチで進められ、昭和11(1936)年6月25日「東書文庫」と命名され、開館しました。表札は明治~昭和期に活躍した中村不折画伯によるものです。
建物は鉄筋コンクリート造り、2階建て(書庫は3層)、延床面積は734㎡でした。書庫内の階段と2層、3層の床や書架は鉄製で大変頑丈に造られました。1階ホールの丸窓、半円形に突き出た窓や玄関の庇を支える2本の円柱など、アール・デコの意匠が用いられ、スクラッチタイル様の黄褐色のタイルを貼った外観は大変モダンなものでした。
開館当初、文庫に集められた資料は約5,500点でした。その後各方面からの援助や有志の方からの資料の寄贈などにより、着々と充実していきました。中でも初代館長の細江省吾の尽力には目を見張るものがあり、後世に語り継がれています。
細江氏は三重県に生まれ、東京高等師範学校を卒業後、北海道から山口までの旧制中学で教鞭をとり、秋田県立本荘中学校長、秋田県立図書館長を歴任の後、当文庫に館長として招かれました。
細江館長の奮闘ぶりについて『出版クラブだより』に「毎日のように教育書購入に奔走し、リヤカー1ぱい2はいと買い集め、洛陽の紙価を高からしめた。」(第117号、昭和47年11月)と記されています。
さらに、昭和13(1938)年には、文部省より明治時代を中心とした検定教科書など約47,000点の寄贈を受けたこともあり、昭和15(1940)年には、所蔵図書は72,000点ほどに達していました。開館翌年に発行された『東書文庫教育図書目録』も、昭和17(1942)年には第4輯が発行され、ようやく図書館としての形態が整いました。
そして、翌18(1943)年、19(1944)年には、時の文部大臣がそれぞれ参観に訪れました。しかし、とても残念なことに、細江館長は昭和20(1945)年7月、空襲のなか、帰宅途中に病に倒れ、終戦を迎えず亡くなられました。館長の他に二人いた職員も前年の夏までに共に召集され、その後は細江館長一人で運営にあたっていました。
戦争末期、昭和20(1945)年4月には、東書文庫の周辺は空襲により一面火の海と化しましたが、社員の奮闘で本社屋・工場・文庫共に焼失を免れ、庭園の木立と共に今日まで当時の姿を残しています。
戦後の混乱期、図書館としての機能と活動が一時停滞したことは否めませんが、昭和28(1953)年に当館内に「東京教育研究所」が設立され研究活動が行われるようになり、これに伴い文庫の閲覧・来館者が次第に増加していきました。
実際に図書館としての運営が本格化したのは林實元氏が文部省を退官し、昭和33(1958)年に本社嘱託、昭和37(1962)年に館長に就任してからです。同年より文庫内に展示室が開設され、実物の教科書の展示を通して日本の教育の変遷が理解できる施設となり、今日まで多くの見学者を迎えています。以降、司書の資格を有する専門の職員が運営にあたっています。
昭和54(1979)年本社創立70周年事業として、書庫・展示室が増築され、延床面積も1,359㎡になり、同時に蔵書目録『東書文庫所蔵 教科用図書目録』の編集が進められ、昭和57(1982)年10月、第3集刊行で完結しました。
平成に入ると、当館に対する需要は益々増え、閲覧・参館者は全国に及んでいます。また、テレビ局、映画制作会社、新聞社、出版社などからの取材も多く、多様なメディアで紹介されています。
平成11(1999)年に、アール・デコ様式を取り入れた建物が「東京都北区指定有形文化財(建造物)」に指定されました。また、平成19(2007)年には、経済産業省の「近代化産業遺産」の中の「製紙業の歩みを物語る近代化産業遺産群」の一つとして、飛鳥山にある「渋沢史料館」、「紙の博物館」などと共に認定されました。そして、平成21(2009)年には、所蔵資料のうち、明治初期から戦後間もない時期までの76,420点が「近代教科書関係資料」として、我が国で最も代表的な資料群であることを評価され、国の重要文化財に指定されました。
所蔵資料の「劣化」の問題は東書文庫が抱える大きな課題です。江戸時代や明治期の教科書は和紙のため痛みが比較的少ないのですが、洋紙で印刷された戦中や終戦直後の教科書の「劣化」は恐るべきものがあります。もちろん書庫や展示室は温湿度、照明の管理を行い、教科書は酸化を防ぐため中性紙の箱に収めるなどの努力を続けています。また、劣化した資料の修復にも取り組むなど、様々な努力を重ねています。
平成26(2014)年7月には謙堂文庫が所蔵していた13世紀後半から19世紀後半にかけての約600年間に編集され、広く普及した初歩教科書約3,300点を譲り受け、中・近世の資料の充実が図られました。(謙堂文庫とは、教育史家石川謙氏が生涯にわたって蒐集したり、寄贈を受けた教育史関係の記録、文書、文献などを所蔵した私設図書館。現在は閉館。)
江戸時代には藩校や寺子屋による教育が普及していました。長い鎖国から脱却し近代化を急ぐ明治政府は、教育により日本を発展させようと考えます。明治以降の教科書には、日本の時代ごとの在り様が映されています。教科書は日本が歩んだ姿そのものと言えます。